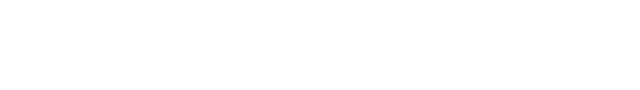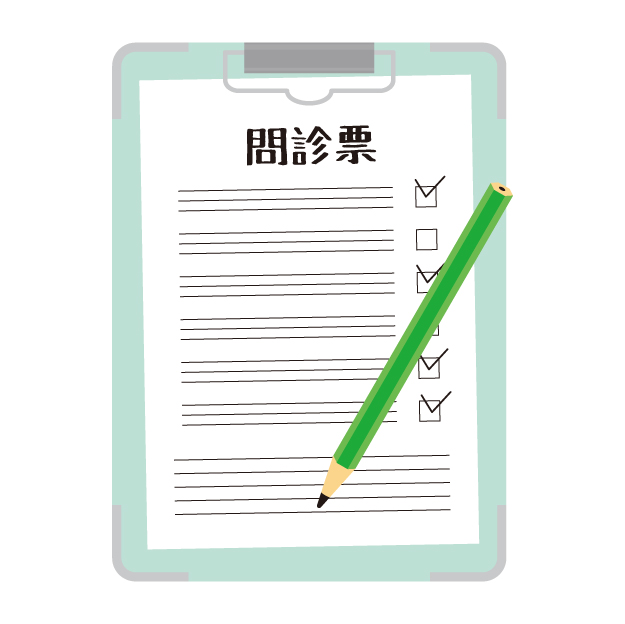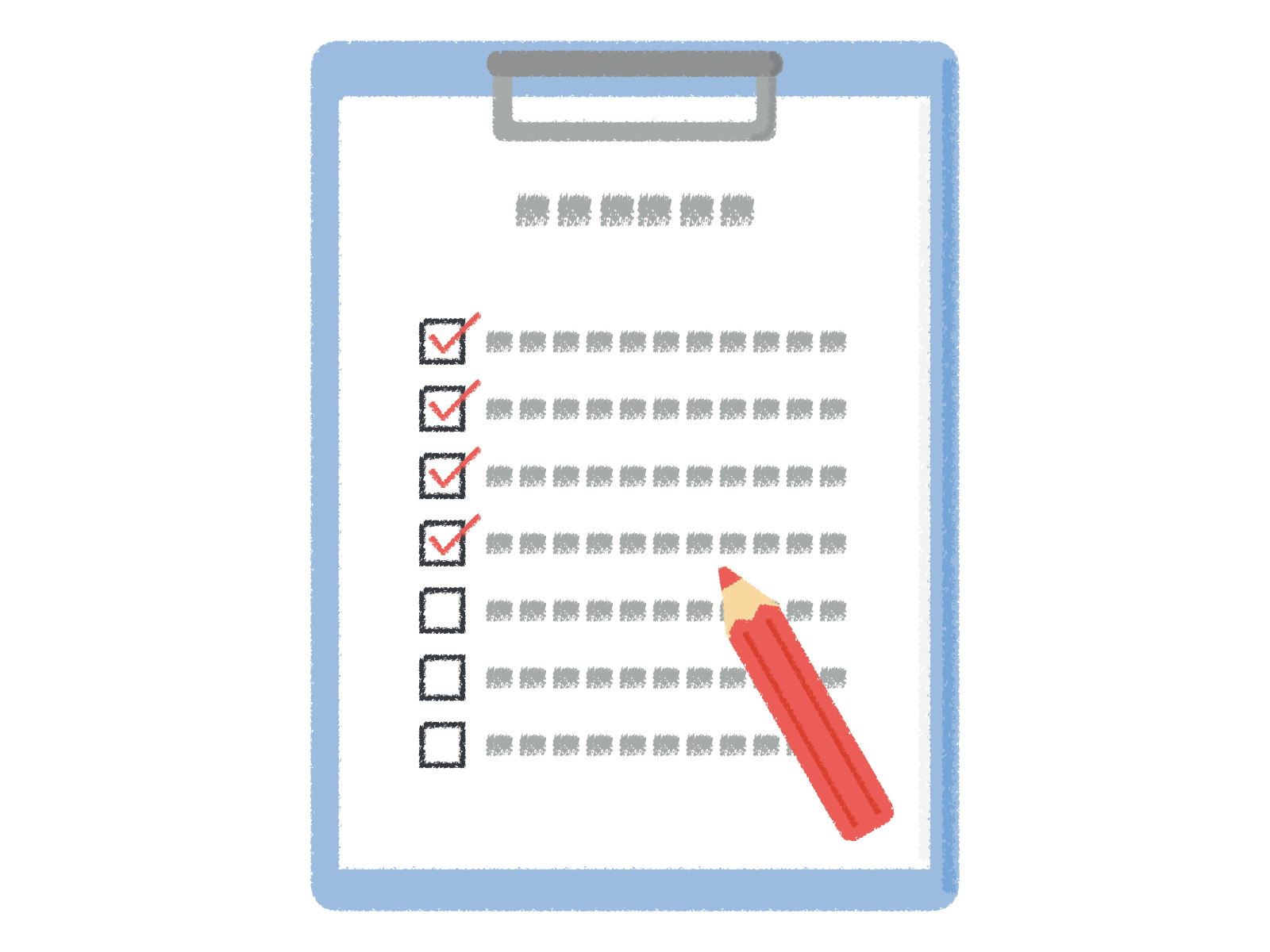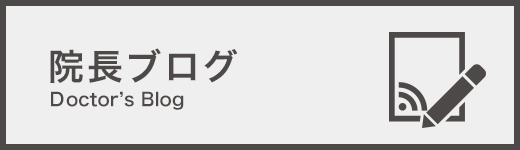医師の偏在と医学部入試の関係について
近年、医師の偏在が問題になっています。
私見ですが、その要因の一つとして医学部入試のあり方が関係していると思います。
長文のため、興味のある方のみお読み下さい。
まずは、現在の国内の状況についてご説明します。
診療科という面では、仕事が忙しくリスクも高い外科、小児科、内科などが敬遠されて医師の割合が減少傾向で、美容外科や糖尿病内科などの医師が増加しています。
地域という面では、都市部に集中し、地方では少ないという状況が続いています。
国や都道府県は医学部に地域枠を設けるといった対策をしていますが、根本的な対策にはなっていないと思います。
その状況には、ほぼ全員が医師となる医学部の学生の資質が関係していると思います。
少子化で受験生全体の数は以前より減っており、医師となっても大変な状況ですが、それにもかかわらず医学部入試は以前より過熱した状況になっています。
1学年で100-120人程度しか入学できない医学部に、数百人~数千人の志願者が集まります。
そのため、医学部に合格するには、レベルの高い塾・予備校で高度な専門的な学習を行うことがほぼ必須となっています。
そのような塾・予備校には最低年間50万円~最高800万円程度の費用が必要です。
医学部を目指す多くの学生は、小学生の頃から塾通いが必須なためさらにお金がかかります。
また私立大学医学部の学費はかなり高額で、6年間で約1900万円~4800万円必要です。
つまり、経済的に余裕がある家庭の子弟のみが医学部に入学でき、余裕がなければどれだけ志の高い学生でも、一部の非常に優秀な学生を除けば、医師にはなれないということです。
もちろん、いずれにしても医学部に合格するにはかなりの努力が必要ですが、経済的な面から入学できる人に偏りができているということは事実だと思います。
また、私立大学の医学部、国公立大学の二次試験は理系科目と英語の学力が高い人から順に合格します。
医学の勉強の多くは暗記であり、医師になってからは数学や物理は全く使わず、臨床医はむしろ文系的な能力が必要であるにもかかわらず、数学や物理などの理系科目や英語の成績が突出した人間が医学部に入学し医師になっているのです。
個人的な話で恐縮ですが、私が文系から医学部に入学できたのは、昔は文系科目だけでも受験可能な医学部もあったことが大きかったと思います。母校の自治医大も当時の受験科目の数学は、数Ⅲはなく、数Ⅱ・Bまでで受験できました。
併願していた国立大学は国語が入試科目でしたが、最近入試科目から外されました。
今の時代なら、私は医師になれなかったかもしれません。
つまり、文系科目が得意だが医師になりたいという学生は、近年医学部から排除される傾向なのだと思います。
なぜそこまで医師になるのに理系科目や英語が重視されなければいけないのでしょうか?
一つは、医学部の学生を選考するのが、研究を重視する大学の教授たちということだと思います。あえて極端な言い方をすれば、大学の先生方にとって最も重要なことは、大学に残り、研究してくれる医師を養成することでしょう。
研究成果を海外に向けて発表するには、英語も必要ですので、英語が重視されるのも理解できます。ただ、国内で臨床医となるなら、たまに英語の論文を読むことはあっても実際に英語を話す機会は少ないです。
大学の先生方は否定されるかもしれませんが、実際には、多くの臨床医志望の人は大学にとっては優先順位が低いのだと思われます。
もちろん、研究が重要であることは言うまでもありませんが、現実的に、病院や診療所で勤務する主に患者さんの診療を行っている臨床医と大学に所属する医師の割合を比較すると、圧倒的に臨床医が多いのは事実です。
にもかかわらず、医学部の入学者の選考をするのは全て大学の医師たちですので、医師の資質に偏りが出るのは当然ともいえるでしょう。
子どもの頃から医師になり、純粋に人の役に立ちたいという想いを持っている人たちが、経済的な面や理系科目が得意ではないという面から医師になれないという状況が多くなっています。
確かに、学業優秀な学生は増えており、研究者を育てるためには理系科目が得意な優秀な学生は必要でしょう。ただ、理系の頭が良い学生は合理的に考える傾向があるため、収入が高く、リスクの低い診療科や都市部に集中して医師の偏在が起こる一因になっているのだと思います。
医師偏在問題を改善するためには、まずは医学部の大学入試のあり方を改善することが必要だと思います。具体的には難しい面もあると思いますが、受験科目などの選考方法や経済的な支援などについて、国や大学の先生方にあらためて検討していただく必要があるのではないかと考えています。